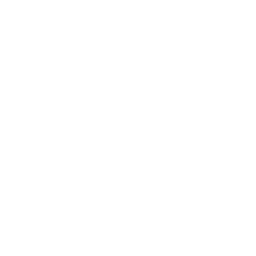94件のひとこと日記があります。
2019/03/03 21:43
仕丁
雛段の五段目 道具を除けば最下段にいる三人 「仕丁」といいます。
ひな祭りのお人形さんは、最上段は天皇皇后、左大臣右大臣は官僚トップ。三人官女も五人囃子も貴族の子女子息。
そんななかで、「仕丁」だけが庶民。
「仕丁」は、律令制の租庸調のひとつで、1里50戸につき2人,中央官庁などに3年交代で無報酬で雑役夫として勤務していたひとたち。食糧など一切は故郷の負担。まあ、税の一種。
平安時代に「ひいな遊び」「流し雛(ながしびな)」という形で原型が始まり、宮廷や武家の間でのみ行われていた「雛祭り」。
1700年ごろから庶民の間でも行われるようになり、18世紀終わりごろには五人囃子、幕末までには官女や随身、仕丁などが考案され、嫁入り道具なども登場した、と言われています。
雛人形に「仕丁」を加えたのは庶民ということです。
最下段にいる「仕丁」の三人は、それぞれ、怒り上戸、泣き上戸、笑い上戸。喜怒哀楽の感情が表現されています。
怒って、泣いて、笑って。下で支えて。
「仕丁」は雛人形の「影の主役」なのかもしれません。
ひな祭りの超簡略歴史
〇ルーツは、中国渡来の「上巳(じょうし)」の節句
日本では
〇縄文〜弥生〜古墳時代…祓いの儀式につかった人の形
〇奈良時代…人形(ひとかた)の誕生
〇平安時代…「ひいな遊び」「流し雛」
〇安土桃山時代…「ひいな遊び」から「雛祭り」へ
〇江戸時代初期…立ち雛、座り雛の登場
〇江戸時代後期…宮廷や武家の間でのみ行われていたひな祭りは、1700年ごろから庶民の間でも行われるようになった。
18世紀終わりごろには五人囃子、幕末までには官女や随身、仕丁などが考案され、嫁入り道具なども登場。
〇明治・大正時代…明治時代の雛人形は、大型で豪壮。家の権勢を誇示するような派手な雛人形が増えていった。人形と道具が一式揃えで出回るようになったのは大正時代中期ごろ。
〇昭和時代…十五人フルセットの七段飾りなどが流行、時代の象徴として飾りも豪華に。
〇平成時代…核家族化や家庭環境の変化、住宅事情などで、コンパクトな雛人形が増えて来ている。